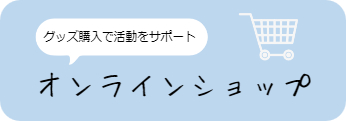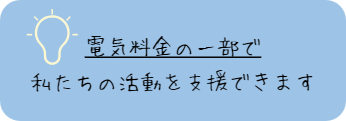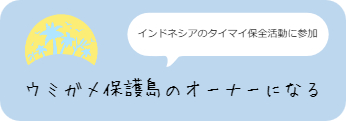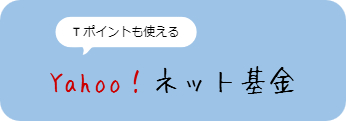| 森元 由佳里 |
| ELNA の小笠原でのボランティア活動に参加したのがきっかけで、小笠原に移住し働くことに。 今まで海や海洋生物とは全く関わりのない人生を送ってきたため、毎日沢山の新しい発見があると感じている。大村海岸の夜間モニタリング調査専属から始まって、今ではウミガメの産卵・孵化シーズン中にあちこちの海岸を駆け回る日々。 ザトウクジラ調査では、カメラマン等を務める。 |
| 近藤 理美 |
| オーストラリアの大学で海洋科学や環境マネージメントを学び、帰国後は海洋生物とは全く関係ない仕事に従事。 海洋環境保全活動への思いが捨てきれず、転職活動をするなかでELNAに出会い入職し、気がつけば世界遺産の島小笠原へ・・・ 調査技術を身につけるべく、ウミガメやクジラに振り回されながらも勉強の毎日。 |
| 坂本 赳哉 |
| マレーシアの大学を卒業後、フィリピンでクジラとイルカを追いかける日々を1年半続ける。コロナ禍の中、オンラインイベントでELNAそして小笠原を知り、スーツケース1つで父島に来島。慣れない「現場」に振り回されながらも、ウミガメのことを勉強中。趣味はおりがみ。ミスチルの大ファン。 |
| 清水 菜々子 |
| 専門学校を卒業し、水族館で魚類担当の飼育員に。飼育していたウミガメの可愛さに惹かれ、野生のウミガメに関わる仕事がしたい!と人生で初めて小笠原へ来てそのまま入職。何もかも初めての島で戸惑いつつも、大好きな日本近海の魚たちとウミガメに囲まれる生活に期待を膨らませ、張り切ってELNAの業務を勉強中。 |
| 松岡 風花 |
| 海と山に囲まれた漁師町で育った、石、生き物、植物をこよなく愛する自然大好き人間。高校・大学は海洋学科に所属。大学卒業後は、自然の家で事務職員に。しかし、もっと外に出られる仕事がしたい!と思い、転職先を探していたところELNAに出会う。ウミガメたちに囲まれる生活に憧れ、勢いのまま志願し入職。小笠原という遠い地で私が出来ることを模索しながら、日々奮闘中。 |