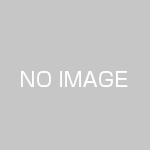- ホーム
- ウミガメの独り言(黎明編)
- アキルさんとの別れ(特別編)
アキルさんとの別れ(特別編)
やっと、「ウミガメの独り言」を書く気持ちになった。これまで、心の中は空虚で何をしても張り合いがなかった。6月4日、僕と東京海洋大生の橋本君は、インドネシア調査に行くために成田空港にいた。午前11時30分発の便に乗り込んだちょうどその頃、インドネシアウミガメ研究センター(YAL)代表のアキル・ユスフ氏がジャカルタの交差点でバイクに乗って右折しようとしていたとき、バイクの後ろを直進してきたバイクに引っかけられて転倒した。僕らは、ジャカルタに午後7時過ぎに着き、ホテルには入れたのは午後8時半近くになっていた。YALの研究員のワヒド氏から連絡があり、翌日午前9時過ぎにYALの事務所に調査の打合わせに行くことを話し、その時にアキルさんが交通事故に遭い、右足を骨折したと聞かされた。
YALの事務所で調査打合わせが終わり、骨折したアキルさんの見舞いに行こうということになり、ワヒド氏と病院に向かった。ちょうどお昼にアキル氏の病室に入り、お見舞いをし、事故の様子や今回の調査のことなどを話した。足の骨折はそれほど悪くはないようだった。最初は、少しおなかが痛いと言っており、2時から検診を受けるとのことであったが、1時を過ぎる頃から激痛を訴えるようになり、目もうつろになってきた。2時の検診が始まるというので、僕らはいったんホテルに戻った。
6月6日、まだ日も明け切らないうちにワヒド氏からホテルに連絡があり、アキルさんが危篤だという。何が起きているのか、分からなかった。9時過ぎに病院に行ったところ、集中治療室からアキルさんの奥さんが出てきて、涙を流しながら僕に透明なプラスチック袋に入った20cmほどの真っ黒に変色した腸をかざし、「これ、アキルの、これアキルの腸・・・・」と、最後は言葉にならなかった。「手術したのか、手術はどうだった。悪いところは全て切り取ったのか。」近くにいた、YAL事務員のエマちゃんに聞いた。エマちゃんは「全部取りきれずに、おなかを閉じた。」と一言だけ。奥さんが「アキルに会ってくれ。」といい、集中治療室の扉を指さした。エマちゃんが案内してくれたけど、アキルさんの意識はなく、血圧は40しかなく、脈拍数も20であった。僕はアキルさんをじっと見つめるしかできなかった。30分くらいで看護士さんから、もういいでしょと言われ、退出した。薬が効くのを待つしかないとのことであった。その時はまだ、アキルさんが死ぬとは思ってもいなかった。
10時過ぎ、僕らはいったんホテルに戻ることにした。病院前からタクシーに乗り、5分も走らないうちにエマちゃんから泣きながらの電話があった。「アキルさんが亡くなった」。僕らは、急遽病院に戻った。ぼくは集中治療室前の奥さん、アキルさんの子供たち、親戚の人たちの泣き顔や途方に暮れた顔を後に、病室に飛び込んだ。アキルさんは静かに眠っているようだった。僕は、アキルさんの腕と胸をつかみ、動けなかった。涙が止まらなかった。どのくらいそうしていたか分からなかった。僕の胸の中に、アキルさんと歩いたインドネシアの島々、アキルさんの笑顔、アキルさんの冗談、アキルさんの困った顔、一緒に泳いだこと、食事の時のこと、そんな風景が次々と流れる。だれかに引き離されるまで、僕はその場を離れることができなかった。
アキルさんと知り合って15年、これが長いのか短いのか知らない。僕に言えるのは、インドネシアのウミガメの調査や保護を、二人三脚で、お互いのあうんの呼吸で、細かい打合わせなどせず、やってこれたことだけだ。敬虔なイスラム教徒であったアキルさん、最初会ったときは僕らに気を使って、ビールに少しだけ口を付けたアキルさん、ウミガメの保護に対しては、強力な牽引車となってくれたアキルさん、無理矢理同行してもらった果てしない調査のときのアキルさん、最近は痛風で調査にあまり同行することはなくなったけど、常に僕らの調査や保護活動のフォローをしてくれていた。時には、理解できないこともあったけど、それもみんなで乗り越えてきた。僕らがタイマイやオサガメの保護活動ができたのは、アキルさんがいたからだ。アキルさんが亡くなって、僕の胸にポッカリと穴が開いた。何をどうしてよいのか分からなくなった。
親戚や家族、会社の同僚(アキルさんは国の公務員でもあった)から慕われ、お葬式や埋葬も大勢の人たちが参列した。イスラム教は土葬である。アキルさんには4人の子供たちがいるが、まだみんな若い。一番上が7月から高校生、一番下は小学校1年生だ。子供たちがお墓に覆い被さり、みんなが帰っていっても動かない。親戚の人たちに引きずられ、車に戻っていく。埋葬から事務所に戻り、YALの職員と奥さんと話をした。その時、亡くなった日の夜明け頃、アキルさんの意識が一時戻ったとの話を聞いた。その時に、アキルさんは「YALをつぶすな」と奥さんにその一言だけ言った。それを聞いて僕は、これからもアキルさんとずっとつき合うことにした。僕が海岸を歩ける限り、アキルさんの気持ちを胸に抱えて、インドネシアと向き合っていくことにした。
僕は、病室で亡くなったアキルさんの腕をつかみ約束した。アキルさんの子供たちは、僕がインドネシアに通ってからみんな生まれている。彼らが、自分たちの父親のことを誇りに思い、社会人になれるまで、「僕が見守るから心配しなくていいよ」。心の中で僕はつぶやいた。(了)