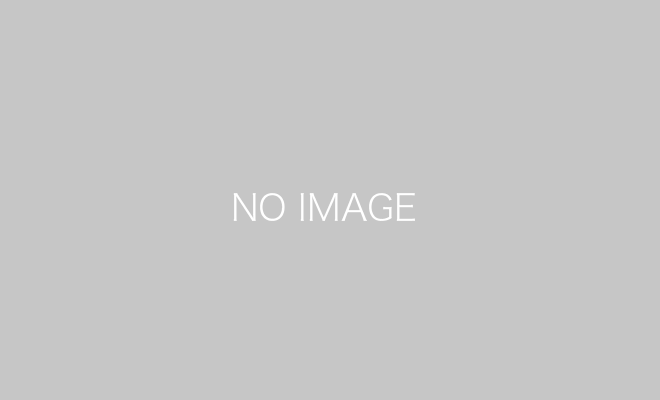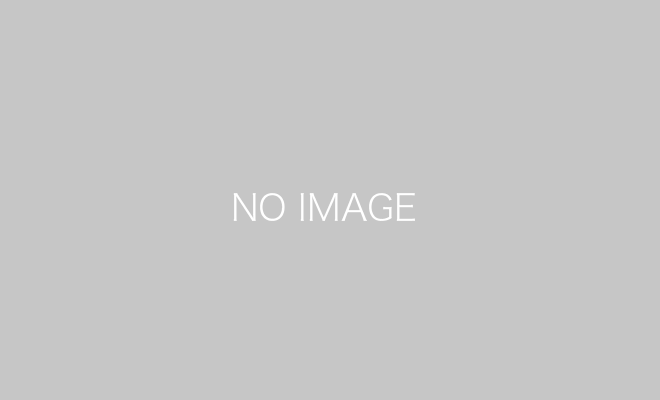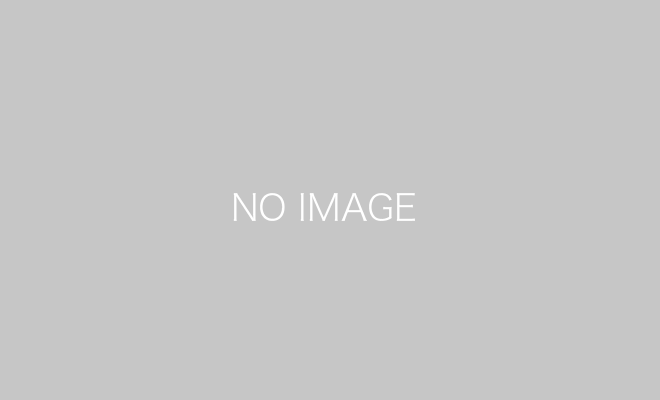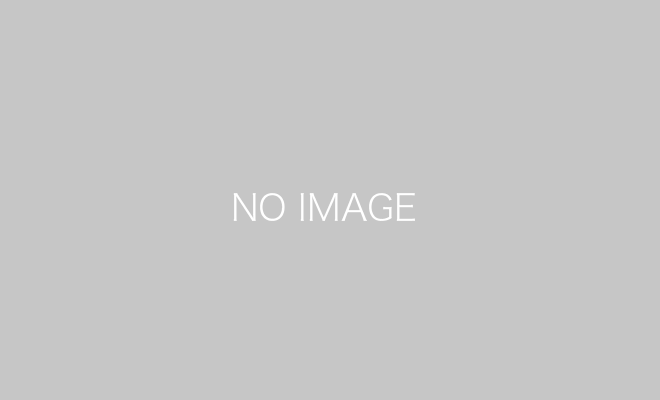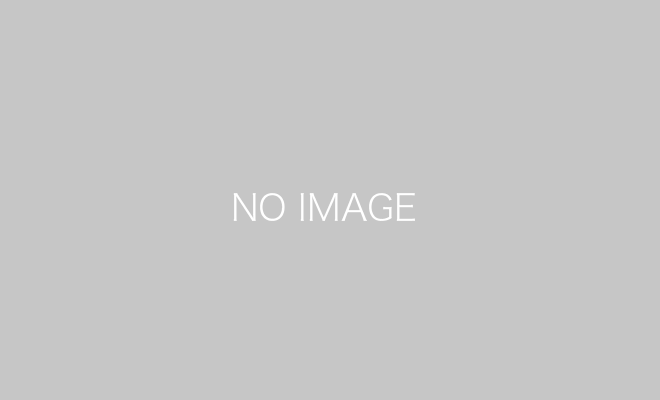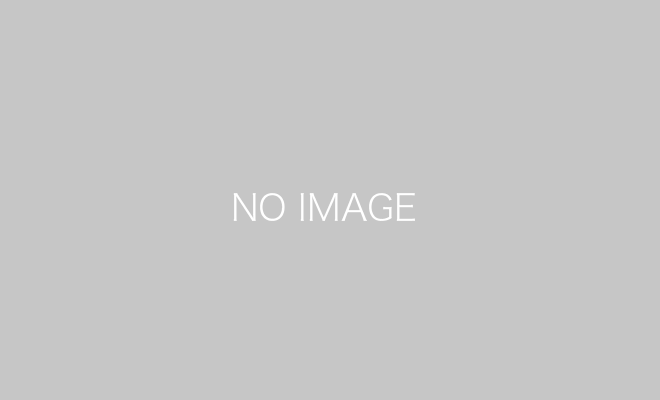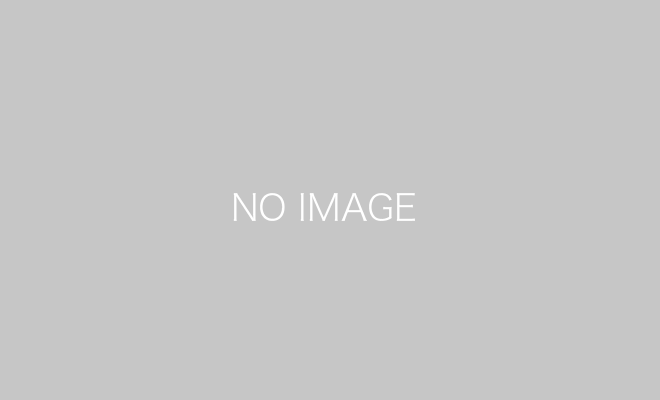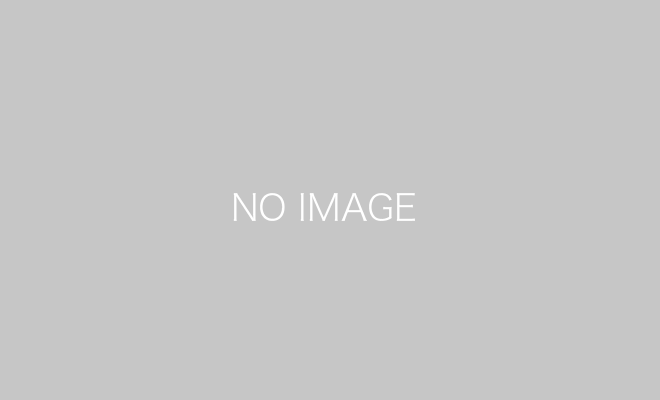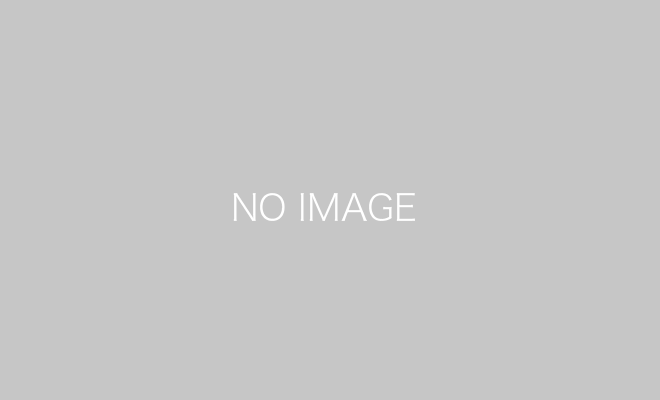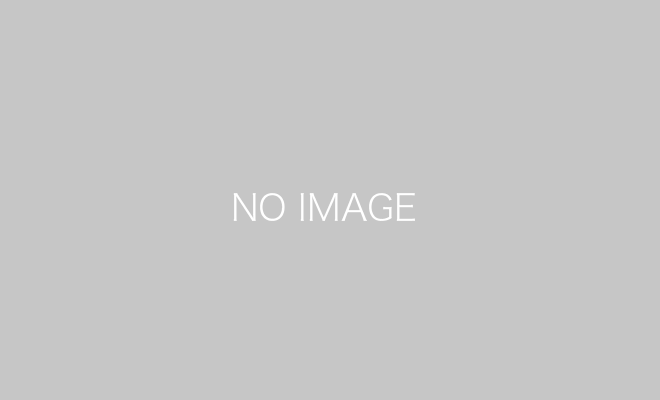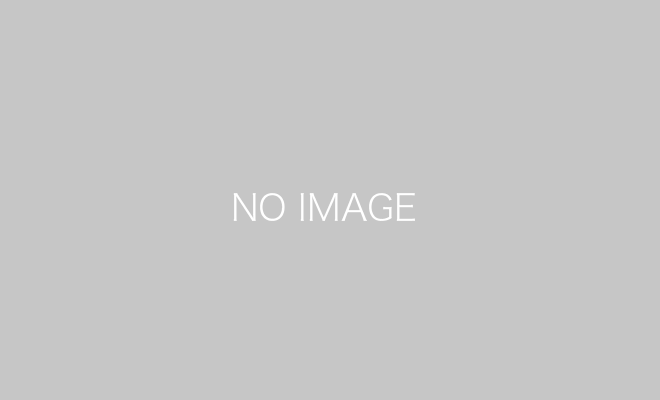
明日(2007年2月2日)から、インドネシアに行く。前回の「ウミガメの独り言」も、この出だしで書いた覚えがあるが、前回の時は出発当日の夜中に…
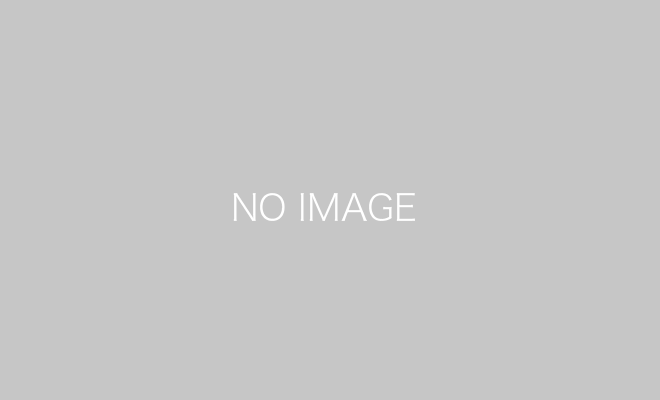
明日(2006年11月29日)から、インドネシアに行く。タイマイの調査である。調査というと標識をつけたり、ふ化率調査を実施したり、ウミガメの…
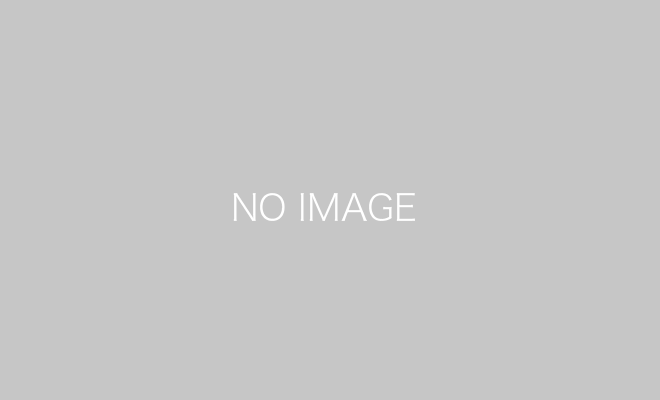
ウミガメばかりではなく、野生の動植物に関してもそうだけど、保護というと現場でその対象を守ることが最も重要な活動であると思われている。本当にそ…
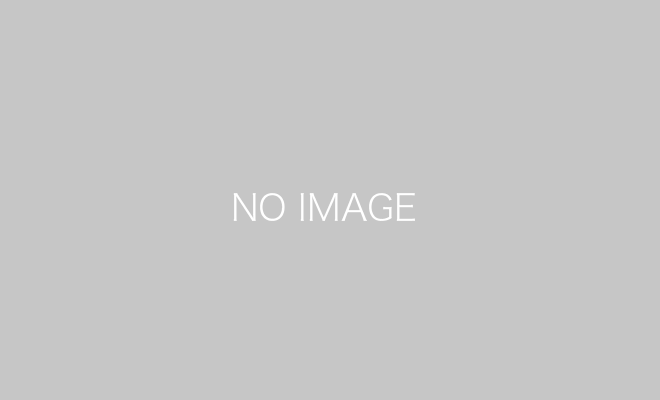
最近、学生や若い人たちが事務所によく来る。ウミガメをやる人たちが増えているのだろう。「ウミガメをやる」と書いたが、まさしく「ウミガメをやる」…
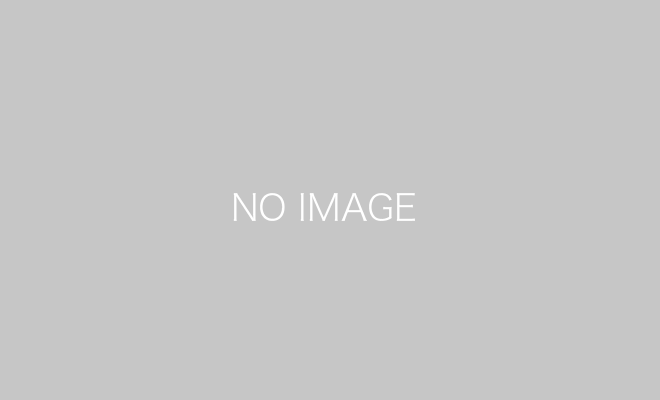
僕は30年間、ふ化後のふ化しなかった卵を割ってきた。これまで、アオウミガメ・アカウミガメ・タイマイ・オサガメ・ヒメウミガメの死亡した卵をみて…
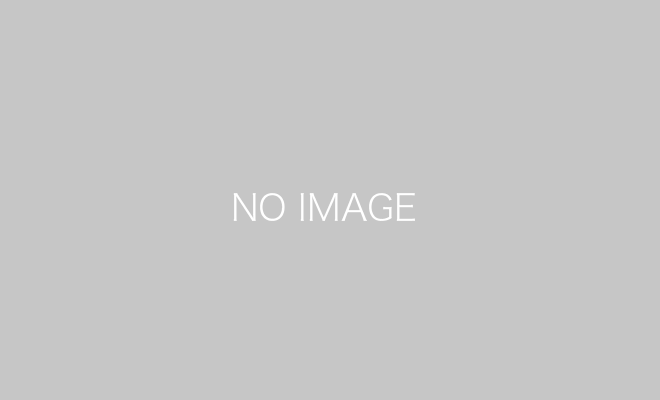
先月の3月8日に、インドネシアから戻ってきた。正確に言うと日本へ一時出国し、昨日到着した。昨年暮れにインドネシア科学研究庁(LIPI)から調…
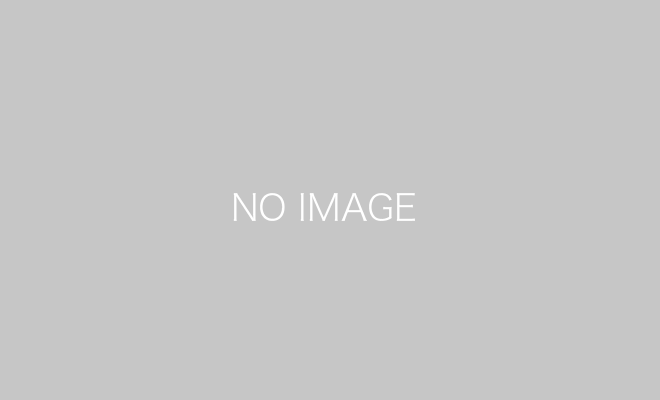
先日、千葉県の館山に泊まりがけで飲みに行った。夕方に館山に着き先ずは旅館の温泉にザブリと浸かる。時計の針が5時を指している。いよいよ戦闘開始…
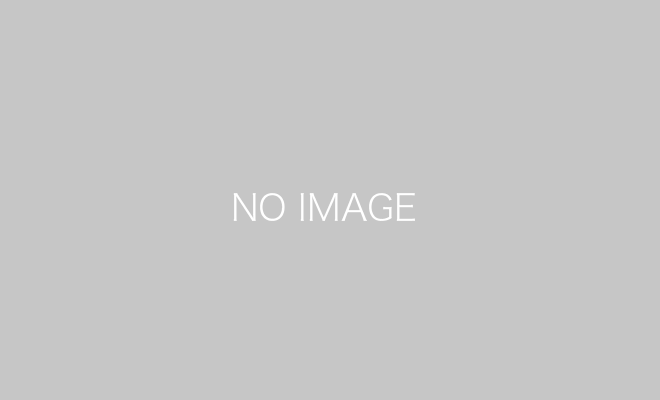
今年9月から10月にかけて2週間ほどELNA の職員の鳴島と小笠原へ行った。父島に着いた次の日からさっそく調査だ。この時期、小笠原ではアオウ…
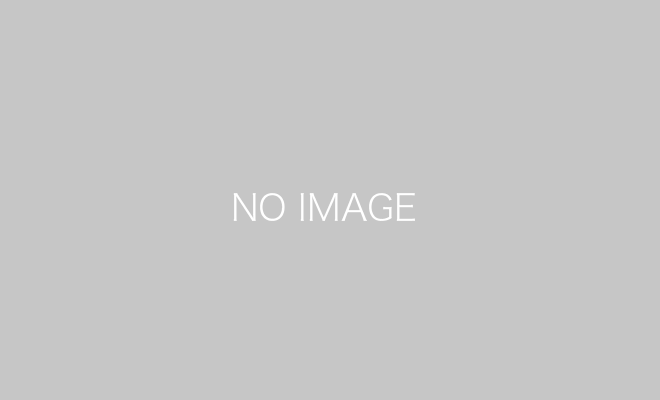
2005年8月21日にインドネシアに行った。オサガメ調査をするためにパプア州のソロンに入ったのは24日だった。そしてジャカルタには27日戻っ…
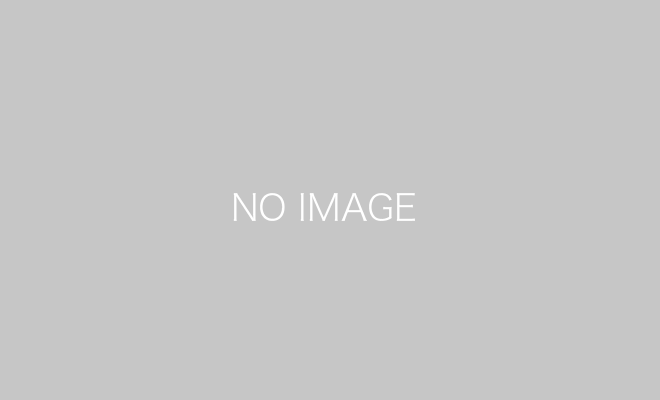
べっ甲という言葉が僕の頭の中から消えて久しい。日本はよその国からほしいだけ輸入して後は知らん顔、だから僕はインドネシアでタイマイの調査と資源…
アーカイブ